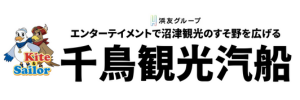企画展「韮山譚索(たんさく)『ハナシ』で辿(たど)る記憶と記録」が2月1日、伊豆の国市郷土資料館(伊豆の国市三福)で始まった。
2023年に創設70周年を迎えた、国学院大学の学生サークル「説話研究会」が協力し、地域の伝承や地元住民の体験談を記録し、次世代に伝えることを目的に開く同展。
同研究会は2023年から伊豆市韮山地区を中心に調査を行い、30~90代の地元住民から約400の話を聞き取った。今回はその中から約30話を選び、パネルや写真などで紹介する。毎年1月28日の祭礼日に「竈(かまど)神社」(南條)で頒布する火災よけのお札と洗米 、「スミンチョ」と呼ばれるお守りも展示する。
パネル展示では、「地域に伝わる俗話や昔話」「干支(えと)にちなむ蛇の伝説」「狩野川台風の体験談」を中心に、地域の文化や歴史を多角的に伝える。地図も制作し、地図上に番号を振ってパネルと連動するよう工夫した。博物館学芸員課程を専攻する生徒のアイデアで、パネルの文字はユニバーサルデザインのフォントを使い、漢字にはふりがなを振り、漢字が苦手な人でも読みやすくなるようにした。
同研究会顧問で同大文学部教授の飯倉義之さんは「研究会の現メンバーが大仁や韮山、長泉、東伊豆などの出身だったことから、伊豆の真ん中で山に囲まれた平地の韮山を中心とした伊豆の国市を研究することになった。現地での採訪をきっかけに同館から声をかけてもらい、これまでの成果を展示する運びとなった」と話す。
同館学芸員の中川典子さんは「思った以上に学生がまとめた説話の量が多くて驚いた。狩野川台風の特集や、時代ごとの説話の紹介はあるが、韮山地区という切り口で近世・中世・近現代を通していろいろな時代の展示がされるのは面白い」と話す。
同研究会の大江夏葵さんは「今回の展示に向けて、カラーの地図を作製した。大学では伝承文学を専攻している。地域で昔から伝わる話は、若い世代に話さないと途絶えてしまう。この展示を見て、それぞれの人がおじいちゃんおばあちゃんなどから昔話を聞き、家族で話すきっかけになれば」と期待を込める。
開館時間は9時~16時30分。月曜と最終金曜休館。入館無料。4月27日まで。